明けましておめでとうございます。今年も旧年中にお世話になった方々を思いながら1年を振り返りたいと思います。一般の方には見えにくい、お寺が檀信徒に提供する価値を、可視化するためにデザインしてきたプロジェクトをまとめます。
<ホームページ作成事業>
この仕事を始めた時、寺院広報にもホームページは必要だと感じていましたが、優先順位を下げていました。理由としては、来寺してくれた人に渡す資料すら無く、そちらを優先していました。しかし、お世話になった実績寺院をネットで検索すると「このお寺で葬儀ができます」と誤った情報が掲載されていました。その現状を見て、取材・記事作成・運営管理まで一括で伴走する「寺院公式ホームページ」事業を立ち上げ、現在2ヶ寺様でサポートをさせていただいています。
<若者向け企画>
鎌倉・顕証寺様で同じ宗門寺院の青年会が集まる青年講を取材し、映像を制作しました。お寺は人とのつながりを支えてくれる場所だと若者層に伝えることが必要だと感じ、活動内容をダイジェストでまとめました。
<檀信徒の後継者インタビュー>
「檀家の子や孫はお寺に来ない」とよく耳にしました。実際に檀家の後継者を取材したところ、菩提寺に対して辛辣な意見を持つ方もいらっしゃいました。しかし、住職パンフレットを事例として紹介すると「住職の人となりがわかると安心できる」と好評をいただきました。住職の人柄を伝えることは、先祖供養を「誰に」お願いするかを重要視している今の世代には改めて大切だと感じました。
<寺院パンフレット制作事業>
これまで販売を中断していましたが「檀信徒の子や孫へ、永代供養の意味合いをする資料がほしい」「お寺での先祖供養を紹介したい」とご要望をいただき、4ヶ寺様で制作させていただきました。
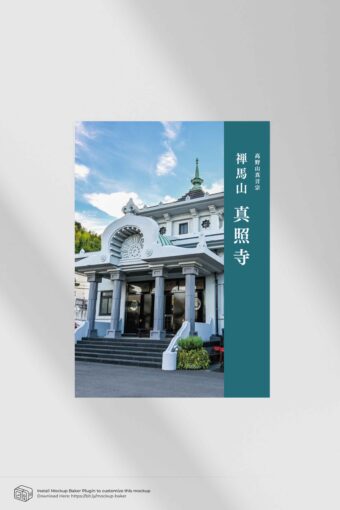
寺院広報活動の最適解は「事例研究」
紹介のお許しをいただいた寺院のうち、ぜひ参考にしてほしいと思う取り組みをご紹介します。弊社の事例から、ご自坊様でもすぐにできることをお伝えします。
<日蓮宗・本興寺様> 人を惹きつける話し方
「お寺で終活相談会」の講演をさせていただいた横浜市にある本興寺様。2月に実施しましたが、みぞれが降る極寒のなか53名の方々にご参加いただきました。
講演では葬儀やお墓の引き継ぎなど、終活の悩みについて檀信徒に取材した相談事例を紹介し、その問いに対して住職が普段どんな回答をしているかをお伺いしました。住職から参加者にいつでもお寺に相談に来てほしいと訴えかけていました。
しかしながら、自分の死に関わる話題なので参加者の表情は不安そのもの。さらに、本興寺様は日蓮宗のなかでも由緒寺院である別格本山ということもあり、檀信徒でさえ普段から住職に気軽に相談できるとは思えなかったでしょう。
そんな空気のなか、講演の最後に浅井住職が趣味のボクシングの話題を始めました。私は「こんなに重い空気の中、そんな話題を出すの?」と正直に思いました。しかし、参加者のみなさんの表情は次第に柔らかいものに変わっていくのがわかりました。ここが重要なのですが、住職はその話題を早々に切り上げ、終了後には残られた参加者一人ひとりに話しかけていました。
仏事を先祖代々から受け継いだだけの檀家さんにとって、仏事以外に住職とフランクに話す機会は少ないでしょう。浅井住職は自分のプライベートを公開することで、相手が話しやすい空気を作られていました。
終活相談会は案内状を発送するため、檀信徒がお寺に関心を持っているかどうかを知ることもできます。法事や墓参りだけでは相手が何に関心を持っているか、悩み事は何なのかはわかりません。
お寺の発信に対しての関心の有無は返信ハガキがひとつの指標となります。欠席されたお檀家さんから「日程が合えば参加したかった」と住職に話しかけられることもあり、お便りをきっかけにコミュニケーションが生まれていました。

本興寺・浅井住職



<曹洞宗・潮音寺様> お寺にある“おかげさま”の文化
駒沢女子大学の学長を務める潮音寺・安藤住職。教学をわかりやすく表現するため、お寺の現場をビジュアルで紹介する記事を作成しました。取材で安藤住職から「日本人にある無意識な宗教観」をお聞きした内容を紹介します。
海外では神とつながる信仰が主流なのに対し、日本では故人とのつながりを願うことを信じます。さまざまな宗教の教えやルーツがあるとしても、日本人には共通して「おかげさま」の文化があるといいます。
そこには、私たちの心のなかに目には見えない「かげ」が自分を支えてくれているという感覚が現れています。何かを頑張るときに「お母さん、見ててね」と故人に祈るのは、亡き人がどこかで見守ってくれているという感覚を無意識に抱いているからだそうです。
人は目には見えなくとも故人を大切な心の拠り所にしている証左であるとお聞きし、故人と遺族がつながる場所を預かる菩提寺の住職としての使命感を感じました。お寺は供養の場所であり、人に安心感を与える場所です。
安藤住職からは「経典の言葉は確かに真実を指し示していますが、本当に大切なのは経典に示された真実を生活の中で実践すること」だとお聞きし、日頃からお寺に伺うことそのものが、その実践のひとつであると感じました。

潮音寺・安藤住職


<日蓮宗・樹源寺様> お寺で美意識を養う
これまで多くの年中行事を取材してきましたが、参列した方々の表情が明るいと感じるお寺が樹源寺様です。こちらの法要ではお供物を参加者に配っています。崎陽軒のシウマイ弁当や池上本門寺名物の久寿餅などは子どもにも喜ばれ、退屈に感じられることもあるお寺の行事のなかで、楽しみのひとつになっています。
しかし、参加者が満足している理由はもっと根源にありました。それはお寺の美しさにあったのです。樹源寺様では境内の整備にこだわっており「お寺に入った時に心が和み、休まる感覚を得るためには非日常感が欠かせません。そのために境内はきちんと整備されていなければいけない」と日比住職からお聞きしました。
観光寺院ではない樹源寺がわざわざ境内をいつも綺麗にする理由を伝えようと、日比住職と打ち合わせを重ねてわかったのは、樹源寺様の「おもてなし」の精神でした。 それはお寺から一方的に提供するものではなく、いただいたお供物に対し檀信徒が付け届けをする気持ちや、お供物を棚からいただく際に参拝者がご本尊にお辞儀をする所作など、美しい儀礼の文化につながっていました。
日本人が持つ美意識のひとつに所作があり、これは教養で身に付くものです。教養とは経験から生まれるものであり、綺麗に整備されたお寺を眺めながら、お供物をいただいた相手に対しお辞儀と御礼をするという経験を、樹源寺様はご家族に向けてアレンジしていました。
日比住職から「人に感謝し良い行動をすると、人は良い波動を生みます。仏事はご先祖に感謝することだけでなく、その善行が回り回って自分にも返ってきます」とお聞きしました。こうした機会をご家族連れで体験したお檀家さんたちの表情は清々しいものでした。




寺院広報とは、お寺のフォロワーを増やす仕事。
昨年は能登半島地震をはじめとした自然災害の発生や戦争の長期化など、コロナ禍が明けても先行きが不透明で不安を抱える1年でした。加えて、自治体の情報隠蔽や金融機関の不祥事なども相次ぎ、何を信じて良いのかわからなくなる事件もありました。いったい信用とは何を指すのでしょうか。
お寺において住職という存在は亡くなった後も称賛されることが多いと感じます。「先代住職が残してくれた本堂が…」「〇〇寺の行事は先々代から続く恒例行事で…」などとよく耳にします。これを語り継いでくれるのが檀信徒であり、その情報の発信源は現住職となります。
しかし、住職自身が寺院の取り組みを発信することが少ないのが現状です。行事案内や施設紹介はホームページ上で広報していても、その活動に込めた想いなどは掲載されておらず、住職は口頭のみでそれを伝える傾向にあります。
過去にはお寺のパンフレットどころか、住職が名刺を渡しただけでも「売名行為だ」などと言われ、社会的に叩かれる時代もありました。30年前にオウム真理教による一連の事件が起きた時には特に顕著だったと覚えています。
気軽に情報が手に入る現代ではその真逆で、正確な情報を届けていないと叩かれる時代となりました。極端な例では、葬儀で僧侶がお布施をもらって帰っただけでも「お経をあげて少し話しただけで帰っていった」「お坊さんの名前を検索しても出てこない」など謂れのない中傷まで受けることすらあります。こうした社会環境において、現在もホームページを持っていない寺院でも、檀信徒からの要望によりホームページ制作を考えられる住職の方も多いのではないでしょうか。
信用に足らない情報が飛び交うなか、透明性が高く正確な情報が求められるようになりました。これからは信用に足ると思われる菩提寺となって、檀信徒に正しい情報を直接届けることがとても重要になります。当社が多くの檀信徒を取材してわかったのは、菩提寺の住職は信用できる相談相手だと思ってもらえていることです。
正しいことを当たり前のように毎日続けられているお坊さんがいて、それを見守ることで安心されているたくさんのお檀家さんがいます。そんなお寺があなたの近くにもありますよ、と広く伝えてくれるフォロワーを増やすことが当社のミッションです。
今日もどこかでお檀家さんへ熱心に仏事をする住職がおられることでしょう。今年も現代のお寺を多くの人に伝えるお手伝いをさせていただきます。 合掌
令和7年元旦
株式会社唯
池谷正明




